|
鏡餅とは神様と人を仲介するものであり、1年間の幸せを願う「晴れの日」に神前に捧げた餅をみんなで分け合って食べることで、神様からの祝福を受けようという信仰・文化の名残りなのです。つまり、鏡餅は神様にお供えしてからいただく尊い餅。「お供え」が鏡餅の別名となっているのはこうしたことに由来しています。
では、なぜ重ねた餅を鏡餅と呼ぶようになったのでしょうか。
ひとつには、丸い餅の形が昔の銅鏡に似ていることから。古来から、鏡は神様が宿るところとされていました。また、鏡餅の「鏡」は「鑑みる(かんがみる)」。つまり良い手本や規範に照らして考えるという意味の言葉にあやかり、「かんがみもち」とよぶ音がしだいに変化して鏡餅になったのだとも言われています。
さらに、鏡餅の丸い形は家庭円満を表し、重ねた姿には1年をめでたく重ねるという意味もあるそうです。
鏡餅の起源は、はっきりとした記録はありませんが、元禄年間のものといわれる書に、丸餅と角餅を重ねた絵が残されており、この頃ではないかといわれています。
様式を重んじることの上に成り立ってきた日本の文化。鏡餅を供える「カタチ」にもさまざまな願いが込められています。
●三方(さんぽう)
鏡餅を乗せる台。
尊い相手に物を差し上げるときには台に乗せることが
礼儀であることから使われています。
平安朝時代にはこの三方は「衝い重ね」
といわれていたそうです。
●橙(だいだい)木から落ちずに大きく実が育つことにあやかって、代々家が大きく栄えるようにと
願った縁起物です。
●御幣(ごへい)・四手(しで)
四方に大きく手を広げ、繁盛するように。紅白の赤い色は魔除けの意味があります。
●海老(えび)
その姿になぞらえ、腰が曲がるまで長生きできるようにと祈るものです。
●裏白(うらじろ=シダ)
古い葉とともに新しい葉がしだいに伸びてくるので、
久しく栄えわたるという縁起をかつぐものです。
●扇(おおぎ)・末広(すえひろ)
末長く繁栄していくようにとの願いが込められています。
●四方紅(しほうべに)
お供え物をのせる色紙で、四方を「紅」でふちどることで
「天地四方」を拝し災を払い、一年の繁栄を祈願するものです。
| 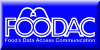 ←フーダックへ
←フーダックへ